
#M&A

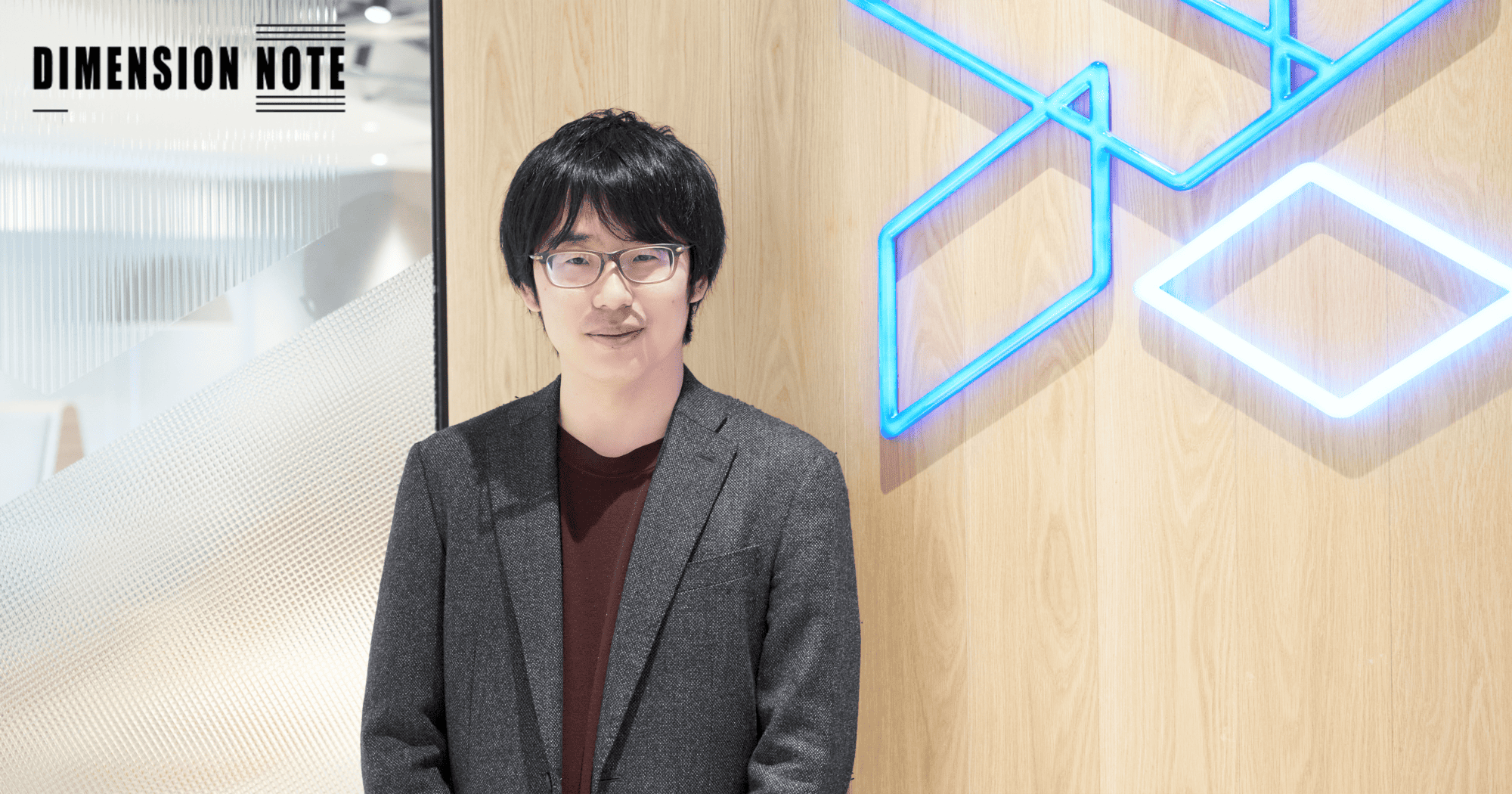
「すべての経済活動を、デジタル化する。」というミッションを掲げ、複数事業・プロダクトを同時並行的に展開する「コンパウンド・スタートアップ」としての挑戦を続けている株式会社LayerX。同社代表取締役CEO 福島 良典氏に、起業家の素養や、組織づくりのポイントなどについてDIMENSIONビジネスプロデューサーの古家 広大が聞いた。(全4話)
ーーLayerXは、ブロックチェーン領域のコンサル事業から始まり、その後SaaS領域へピボットされましたよね。2度の起業をご経験されましたが、起業の具体的な経緯について、お聞かせいただけますか。
日本ではデジタル技術やソフトウェア技術が十分に活用できていません。
人口減少が進む中、生産性の低さや技術活用の遅れから、デジタル後進国と言われ続けています。
これはメディアでも散々指摘されている問題ですが、私自身もこの課題は20年後、30年後の日本に重くのしかかるだろうと考えていました。
そして、少し不遜な言い方かもしれませんが、「自分にはこの状況を変えられる」と思ったんです。
自らプロダクトを作り、様々な企業のデジタル化を支援することを起業家として「やらずにはいられない」という想いと、この変革のチャンスを掴めるという確信がありました。
こんな偉そうなことを言っていますが、実は私自身、それまでBtoB事業の経験も、大手企業向けの営業経験もありませんでした。それでも「ただ始めたくて仕方がなかった」というのが起業の経緯ですね。
ーーデジタル化というと非常に広い領域ですね。御社の法人支出管理領域だけでなく、不動産Techや動画クリエイティブの世界など、デジタル化の対象は幅広いと思います。その中でブロックチェーン領域から始めて、その後SaaSへと展開された理由についてお聞かせください。
デジタル化によって過去30年、一番大きく変化をしたのはメディア産業だと思います。様々な産業がある中で、メディア産業の次にデジタル化が進むのはどの領域だろうと考えた時、それは金融だと確信しました。メディアの性質がデジタルであるのと同様に、お金も本質的にデジタルなのです。
1万円札という物体は存在しますが、その価値は1万円札という紙ではなく、データにあります。
お金は本質的にデータであるのに、なぜソフトウェアが十分に介在していないのか、それが大きな疑問でした。
ブロックチェーンは通貨を発行する技術です。
金融領域のデジタル化は、メディア産業の次の大きな波になると確信し、まずはその領域での情報が集まるポジショニングを取ろうと考え、ブロックチェーン領域のコンサル事業を始めました。
率直に言えば、この事業自体は失敗でした。しかし、そこでのトライがその後のピボットにつながっています。

SaaS事業において私たちが注力しているのは企業のお金のワークフロー、法人支出(※直近は人事領域、債権管理の領域にも進出)の領域です。
多くの企業が請求書を紙でやり取りし、目視でチェックし、手作業で銀行口座に送金をしています。
ヒアリングを進める中で、多くの人がこの業務に課題を感じていることがわかりました。しかも、ミスをした時の影響が非常に大きく、強いプレッシャーがかかります。
金融周りの業務はこれほど明確なペインがありながら、なかなかデジタル化が進んでいません。
このような不自然な領域こそ、次のデジタル化の波が強く押し寄せると確信し、参入を決めました。
ーーまさに今、金融周りの業務革新が必要な一方、法人支出管理においては創業時に先行企業がいたと思います。後発参入する際、その状況をどのように捉え、勝ち抜くシナリオを描いていたのでしょうか。
実は、競合は気にしていませんでした。
顧客体験の中で、何にどれほど強いペインを感じているかの方が重要だからです。
参入の際、競合は一切気にしません。それよりも私たちが顧客体験を10倍良くできそうか、というところだけを考えて参入しています。
ーーつまり、これから新しく企業を立ち上げる際、先行企業が存在していても、競合の状況よりも、自分たちがどれだけインパクトを与えられるかの方がはるかに重要だということですね。
ある本で読んだのですが、ユニコーン企業を分析した結果、参入時に競合がいたケースが7割程度もあったんだそうです。大成功するスタートアップは全くの新規の市場で生まれるというのは、実は誤解なんです。
マーケットリスクを取るか、オペレーションリスクを取るかという話で、競合がいるということはオペレーションリスクを取っているということです。
逆にマーケットリスクを取ったAirbnbやUberには競合がいなかったと思うんです。
競合がいない分、そもそもビジネスとして成り立たない確率の方が高かったと思います。まず自分がどういう類のチャレンジをしているのかというメタ認知は大事です。

ーーということは、領域選定においては競合の存在は気にしないが、事業戦略においては競合も調査するということですね。
もちろん分析はします。しかし、大切なのは、それを理由に撤退や参入を決めるのではなく、その分析を経たうえでもなお、自分の心からの想い、つまり「ここを変えたい」とか「自分たちならできる」という思い込みを持っていられるかを重視します。
実際、プロダクトの必要性はお客様が判断してくれます。プロダクトを出しても、お客様に全く選ばれなければ撤退せざるを得ません。
遅かれ早かれお客様が判断してくれるので、プロダクトを出す前から机上で議論しすぎずに、自分たちが本当に自信あるものを自信を持って作ればいいのではないか、と思いますね。
ーースタートアップではT2D3の売上成長率達成を目指すべきだという考えがあります。これを達成するには、新しいプロダクトを継続的にリリースしていくのが有効な手段の一つではないかと思いますが、リソースの限られるスタートアップにおいて、2つ目以降のプロダクト開発は何を重視して優先順位付けすべきでしょうか。
結論で行くと、リソースは問題ではなく、経営者としてどうしたいか、どんな勝ち筋を描いているか、の意思で決めるべきです。
まず、一つのプロダクトで最高のスピードを出せるチーム規模は何名か、という問いを考えてみましょう。
これは各社の経営者、エンジニアの能力、プロダクトの複雑度やスコープ、成熟度によって異なるため、一概に「5人」「10人」「100人」とは言えません。
ただし、プロダクトの立ち上げ期において、一番スピードが出るサイズは5〜10人ほどのチームサイズです。それ以上のエンジニアを投入してもプロダクト開発が加速するということは、起きません。
2つ目以降のプロダクト開発のタイミングは、リソースの問題というよりも、決めの問題なのです。なのでリソースの多寡で判断するのではなく、今このタイミングでこのプロダクトを出さないとだめといった経営者の嗅覚で決めるべきです。
重要なのは、「新規プロダクトを再現性を持って作れる能力」を持った人材が何人いるか。この能力は極めて希少です。この希少な人を思い切って新規プロダクトに配置するという勇気が重要になります。
加えて、最近のコンパウンド・スタートアップと呼ばれる、複数プロダクトを同時提供する企業の最大の強みは「人材の採用力」です。資金調達力でも営業力でもなく、「創業者的マインドを持ち、プロダクトを作れる人材」を採用できる能力なのです。
例えば、コンパウンド・スタートアップの代表例であるRipplingには100名超の「元創業者」がいます。
LayerXも例外ではなく、創業者という定義は難しいものの、CTO経験者が十数名、COO・CRO経験者が十数名在籍しています。いわゆる「立ち上げ人材」が数十名在籍しているということです。
結局、新規プロダクト開発のボトルネックが「創業者的マインド」やそれに準ずる「新規プロダクトを再現性を持って作れる能力」なのだとすると、まずはそういった人材の採用から始めることが先決です。
あとはそもそも論ですが、コンパウンド・スタートアップにおいては、次に作るべきプロダクトを迷っている時点でやめた方がよいです。

ーーそれは2本目の開発を始めるにあたって、調査が不十分ということでしょうか。
というよりは、コンパウンド・スタートアップを経営する際において、ボトルネックは常にアイデアではなく人です。おそらくコンパウンド・スタートアップを志向する経営者の皆さんの頭の中に、次に作るべきプロダクトはもう存在していると思います。それは日々接しているお客様との対話から明らかになっているはずです。
もしそうでないのであれば、そもそもコンパウンドというやり方が適したマーケットではない可能性が高いです。
私は何でもかんでもコンパウンドという戦略を取ることが正しいとは思っていません。コンパウンドが適したマーケットは想像以上に少なく、言葉が流行っているからといって、無理に適用すると悲惨な結果を生みます。レーザーフォーカスして1つのプロダクトを磨き込んでいくほうが、ほとんどのスタートアップにおいては有効なのではないでしょうか。
ーーLayerXの場合、法人の支出管理から始まり、現在は人事の領域に展開しています。支出管理の次に勤怠管理へと展開された背景について、お聞かせいただけますか。
これはコーポレート業務をしている人からすると、とても自然な流れです。「経費精算と勤怠は実は全く同じ構造をしている」というシンプルな話です。
もう少し詳しく説明すると、コーポレート業務において大きな負担の一つが組織図の管理です。かつその管理が複数システムにまたがっています。
経費精算の場合、まず上長に承認をもらい、その後部長の承認を得る、といった流れがあります。この承認経路って勤怠のときも全く同じですよね。
もしこのとき経費精算と勤怠のシステムが分かれていると、どうなるでしょうか。
組織変更があれば組織図が変わります。それに伴い経費精算の申請ルートも勤怠の申請ルートも変更が必要です。これを四半期ごとか毎月メンテナンスしなければなりません。新入社員が入社した時や、マネージャーへの昇格、降格があった時も同様です。
『バクラク』を使えば、一度承認経路を設定すると、経費精算も勤怠でもその経路が使えます。一方システムが分かれていると、経理チームと人事・労務チームが連携しながら、組織図の変更をシステムに反映しないといけません。この組織図の同期という業務が不要になるのです。経費精算と勤怠を同じワークフローで管理できる、これが大きな理由です。
「経費精算と勤怠を同じシステムで揃えたい」というニーズはバクラクのリリース当初から、お客様より伺っていました。当初、私も「なぜ経理の業務である経費精算と、労務の業務である勤怠のシステムを統一したいのだろう」と疑問に思っていました。そこでお客様にヒアリングを重ねていくと、先程の「組織図管理の話」というニーズに行き着いたのです。
このように、我々のプロダクト群は最初から「こう展開していくぞ」と見通していたわけではなく、お客様との対話の中で、表面的にはわからないニーズにたどり着いてます。
SaaSの常識からすると、例えばバイヤーを変えない方がいい、経理のプロダクトなら経理向け機能だけを拡張すべき、同じドメイン知識の領域に集中した方がいい、といった定説があります。そのため、一見すると奇妙に見えるかもしれません。
しかし、顧客起点のプロダクト開発という観点では、経費精算と勤怠を統合するのは、とても自然だと考えています。
ーー生成AIプラットフォーム『Ai Workforce』 にも同じようなことが言えるのでしょうか。
まず、新規事業の選び方については、隣接事業と飛び地事業という考え方があります。
隣接事業は既存のプロダクトを起点に、お客様に丁寧にヒアリングを重ねることから着想を得られます。
一方、飛び地事業は大きな環境変化を敏感に読み取って、少人数で既存事業の制約から離れて立ち上げます。
両方の事業に共通するのは、繰り返しになりますが「何をやるべきか」について、創業者(もしくは創業者的人材)が感じ取るしか無いということです。その感覚がないのならやらない方がいい。
このように、隣接事業の拡張なのか、環境変化に対応する飛び地事業なのかによって、それぞれの立ち上げ方は大きく異なります。そういった違いをきちんと理解した上での意思決定が非常に重要なポイントだと考えています。
Ai Workforceは「生成AI」という大きな環境変化に対して、飛び地事業として始めました。これは共同代表の松本の強いリーダーシップで、「意図的に」飛び地として立ち上げています。
生成AIが世の中を変えていくというのは、皆さんもコンセンサスが取れていると思うんですが、具体的にどう変わっていくのかについては、まだコンセンサスが取れていない状況です。
Ai Workforceが狙っているのは、今までSaaSが解決できなかったミドルないしはロングテールの業務を、一つのプラットフォームで解決することです。
例えば皆さんも普段ChatGPTを使って、英語の文章を翻訳して、要約したりしていると思うんです。さらにはその論点をまとめて新しい文章を生成するといったこともできる、これらを1つのプラットフォームでできますよね。しかし、既存の翻訳ツールではそんなことできませんよね?
あくまで一例ですが、生成AIのすごさは1つのモデルで、複数のタスクが解けることにあります。この性質によって、従来のソフトウェアでは実現できなかった柔軟性・カスタマイズ性を実現します。
SaaSはカスタマイズしないことを前提に作られますので、必然的に「汎用的な業務」を「標準化する」という作りになります。
一方、Ai Workforceは非構造かつ非汎用的な業務を、AIの柔軟性によって一つのプラットフォーム、一つのインターフェースで解決しています。ここは従来、個別開発で解決されていた部分なのですが、生成AIの登場によって大きな構造変化が起ころうとしている領域です。
ここに新しいソフトウェアのチャンスが生まれるという仮説で構想を立ててAi Workforceは進めています。
先ほどの話でいうと、バクラクでカバーしきれていないお客様層やスーパーエンタープライズでは、カスタマイズが強く求められ、標準的な機能だけでは満たせない周辺業務の課題があると認識していました。
そこへ生成AIが登場した瞬間に「これで解決できるかも」という、誰もやっていないチャンスが見えてきて、松本(LayerX代表取締役CTO)がリーダーシップを発揮してくれました。
生成AIのユースケースはチャットだけでは終わらない、その先にワークフローの革命が来る。そこで今のSaaSとは異なる新しいSaaSが生まれるはずだと、という方向性です。
>次のページ 第3話 「「AIを活用し、評価基準の統一化を図る。」株式会社LayerXの人材採用術 / 福島良典CEO」
>前のページ 第1話 「『すべての経済活動を、デジタル化する。』株式会社LayerX 福島良典CEOの「起業家に必要な3つの素養」とは」
>LayerXの採用情報はこちら
>LayerXの公式HPはこちら

古家 広大
早稲田大学卒業後、三井住友信託銀行に入行。 広島にて個人向けFP業務を行った後、大阪にて法人RMを経験。非上場からプライム市場の企業まで担当し、融資や不動産など信託銀行の幅広いソリューション営業に従事。また、ESGやSDGsをはじめ、CGC改訂への対応支援も行い、グローバルで勝ち続ける企業への成長を非財務領域も含めてサポート。 2022年DIMENSIONに参画。LP出資者からの資金調達と国内スタートアップへの出資・上場に向けた経営支援を担う。

#M&A

#インタビュー

#インタビュー
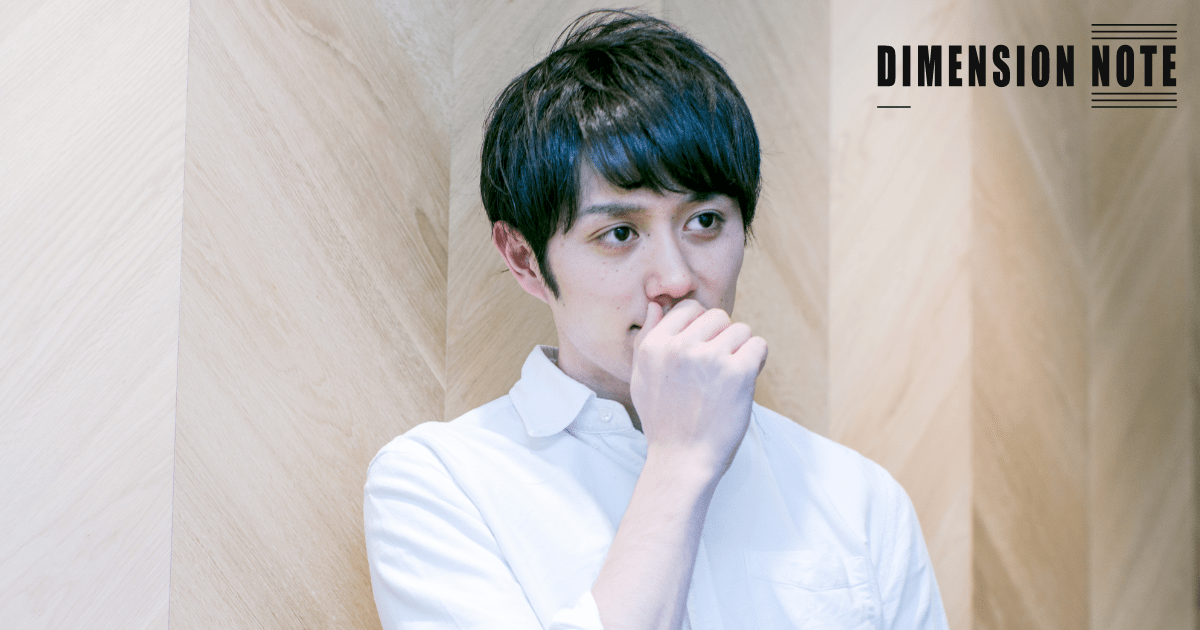
#ビジョン

#起業家の素養

#インタビュー
 1
1
#M&A
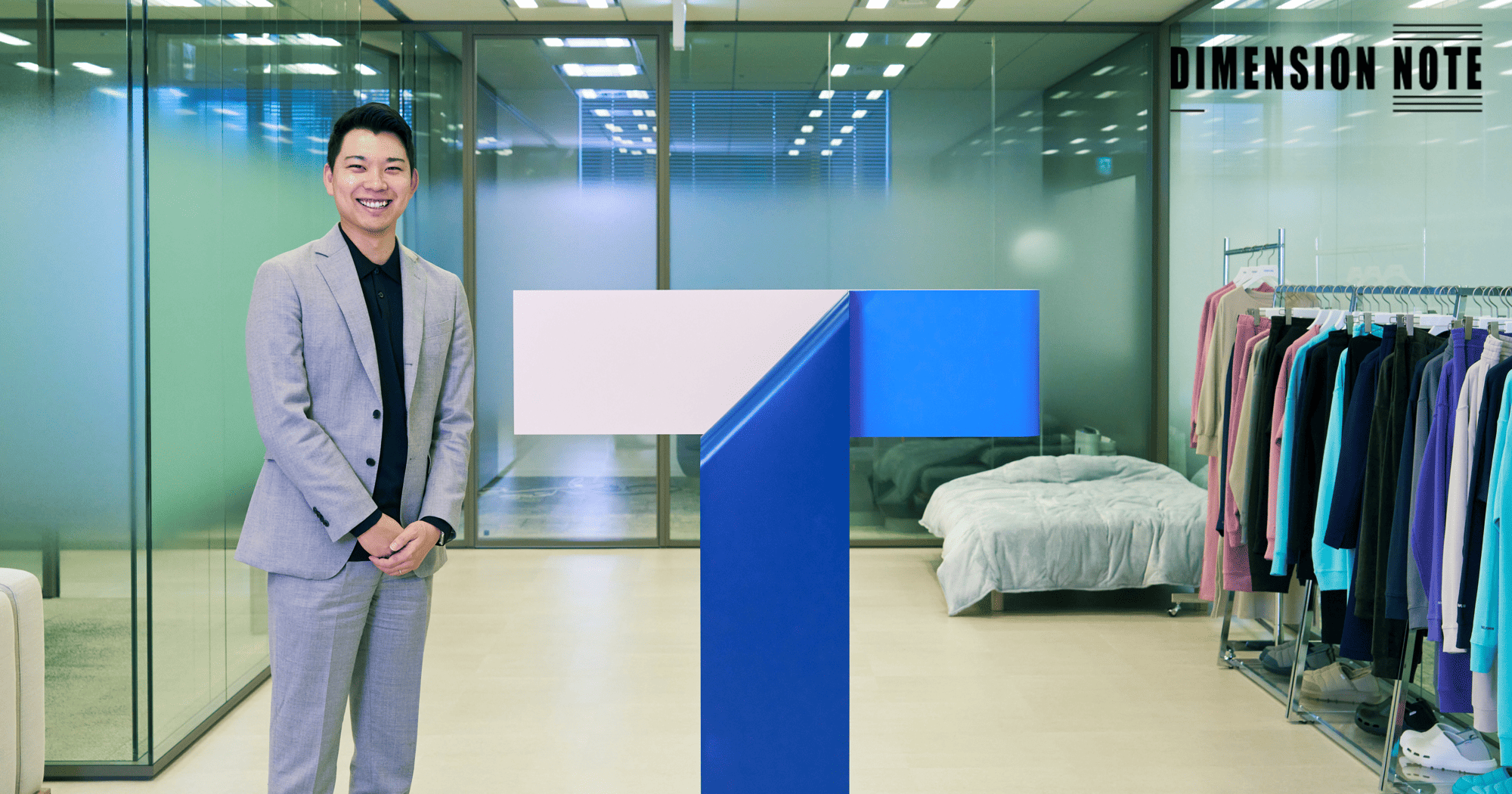 2
2
#インタビュー
 3
3
#ビジョン
 4
4
#経営戦略
 5
5
#インタビュー
 6
6
#インタビュー
This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.